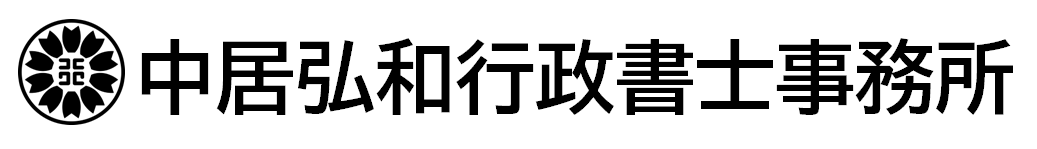投稿日:2024年2月10日 | 最終更新日:2024年9月12日
こんにちは。行政書士の中居弘和と申します。
建設業許可を取得するには6つの要件があります。
それぞれの要件について順次説明させていただきます。
| 【目次】 1.営業所に経営業務の管理責任者等がいること (1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置」について (2)「常勤役員等」って? (3)「建設業に関し」って? (4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」って? (5)「5年以上の執行役員等としての経営管理経験について(基準イ(2))」って? (6)「6年以上経営業務を補佐した経験について(基準イ(3))」って? (7)「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験、「業務運営の経験」、「直接に補佐する」」って? (8)「役員等に次ぐ職制上の地位」って? 2.営業所に専任技術者がいること (1)「専任の者」って? (2)「実務経験」って? (3)他業種・経営業務の管理責任者との兼任、指導監督的な実務経験について (4)専任技術者になれるのはどんな人?(一般建設業許可の場合) (5)専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業(※1)以外)の場合) (6)専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業の場合)) (7)専任技術者資格一覧 3.社会保険等に加入していること (1)「営業所」について (2)「雇用保険」について (3)「健康保険の加入が必要な事業所」について 4.誠実性があること 5.財産的基礎・金銭的要件を満たしていること (1)一般建設業許可の場合 (2)特定建設業許可の場合 (3)各種語句について 6.欠格要件に該当しないこと |
1.経営業務の管理責任者がいること
(1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置」について
まず、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置」についてです。
許可を受けようとする方が法人である場合は常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のイ、ロ、またはハのいずれかに該当することが必要になります。
| イ 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し、次のいずれかに該当する者であること (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。 (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。 (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。 ロ 常勤役員等のうち1人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該役員等を直接に補佐する者として(3)~(5)に該当する者をそれぞれ置くこと (1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。) (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者。 (3)5年以上の財務管理の業務経験を有する者 (4)5年以上の労務管理の業務経験を有する者 (5)5年以上の業務運営の業務経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの |
これらの要件について、少し詳しく説明させていただきます。
(2)「常勤役員等」って?
では、要件にある「常勤役員等」とはどういうものでしょうか?これは、「法人」の場合と「個人」の場合で異なります。
「法人」の場合 → 役員(※1)のうち常勤であるもの(※2)
「個人」の場合 → 事業主本人またはその支配人(※3)
(※1)
「役員」…業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
「業務を執行する社員」…持分会社の業務を執行する社員のこと
「取締役」…株式会社、特例有限会社の取締役のこと。
「執行役」…締め委員会等設置会社の執行役のこと。
「これらに準ずる者」…法人格のある各種組合等の理事等のこと。
(※2)
「役員等」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まれません。
(※3)
「支配人」…事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、商業登記されているものに限ります。
(3)「建設業に関し」って?
全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別はなく、全て建設業に関するものとして取り扱います。
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」って?
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
また、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
なお、常勤役員等が営業所の専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。
(5)「5年以上の執行役員等としての経営管理経験について(基準イ(2))」って?
①「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及びおよび命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
②建設業に係る5年以上の執行役員等としての経験については、建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当します。
(6)「6年以上経営業務を補佐した経験について(基準イ(3))」
①経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、支店長又は営業所長に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
②建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、該当します。
③建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。
(7)「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験、「業務運営の経験」、「直接に補佐する」」って?
「財務管理の業務経験」…建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験(役員としての経験を含みます。以下同じです。)をいいます。
「労務管理の業務経験」…社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
「業務運営の経験」…会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。
これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
(8)「役員等に次ぐ職制上の地位」って?
申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。
【お電話はこちら】【お問い合わせメールはこちら】
2.営業所に専任技術者がいること
専任技術者とは、簡単に言うと、その業務について専門的な知識や経験を有する方のことです。
許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者をその営業所ごとに置く必要があります。
(1)「専任の者」って?
専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、他社で常勤することはできません。また、次に掲げるような者は、専任の者とはいえません。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
なお、専任技術者は、建設業の他社の技術者や、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
(2)「実務経験」って?
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算することはできません。
(3)他業種・経営業務の管理責任者との兼任、指導監督的な実務経験について
2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしている者が、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が営業所の専任技術者になることができます。
勤務場所が同一の営業所である限り、経営業務の管理責任者と専任の技術者を兼ねることができます。
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。したがって、発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、発注者の側における経験または下請負人としての経験は含まれません。
(4)専任技術者になれるのはどんな人?(一般建設業許可の場合)
許可を受けようとする業種が一般建設業許可の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
イ 学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)・中等教育学校指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
②一定の国家資格等を有する者
③学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの
④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
(5)専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業(※1)以外)の場合)
許可を受けようとする業種が特定建設業許可(指定建設業(※1))以外の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
イ 一定の国家資格等を有する者
ロ 左欄のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、かつ元請としてその金額が消費税を含む4500万円以上(S59.10.1からH6.12.27までにあっては3000万円以上、S59.9.30以前にあっては1500万円以上)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(※1)指定建設業とは土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種です。
(6)専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業の場合))
許可を受けようとする業種が特定建設業許可(指定建設業)の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
イ 一定の国家資格等を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又は(上記5.の)ロと同等以上の能力を有すると認めた者
(7)専任技術者資格一覧
専任技術者の資格の一覧はこちら(岩手県で公開している手引きを引用したものです。)。
【お電話はこちら】【お問い合わせメールはこちら】
3.社会保険等に加入している
許可の取得にあたっては健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業所である旨の届書を提出した者であることが必要とされています。
(1)「営業所」について
建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条又は厚生年金保険法第8条の2などの規定によりにより、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業でなくなったものとみなされた営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含まれません。
(2)「雇用保険」について
雇用保険については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第9条の継続事業の一括の手続きにより一の事業とみなされた事業に係る一の事業の事業所以外の事業所である営業所についてもここでの「適用事業の事業所」には該当しません。
雇用保険について、営業所が一の事業所として認められず雇用保険事業所非該当承認申請書を提出している場合は、「雇用保険法の適用が除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しの提出が必要です。
(3)「健康保険の加入が必要な事業所」について
健康保険等の加入が必要な営業所であるかについては、様式に記載された人数で「従業員数」を確認します。
なお、保健当局等から指導を受けた等、記載が実態と異なっており、本来届書を提出すべき営業所であったことが確認できた場合は「虚偽申請」として取り扱われますので注意が必要になります。
【お電話はこちら】【お問い合わせメールはこちら】
4.誠実性があること
【概要】
建設業法では次のように定められています。
【建設業法第7条第3号】
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
「不正な行為」…請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為のこと。
「不誠実な行為」…工事内容、工期等について請負契約に違反する行為のこと。
【お電話はこちら】【お問い合わせメールはこちら】
5.財産的基礎・基礎要件を満たしていること
財産的基礎・金銭的要件の判断基準は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表によります。
(1)一般建設業許可の場合
請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要になります。
その要件は、以下の(イ)~(ハ)のいずれかに該当する必要があります。
(イ)自己資本の額が500万円以上であること
(ロ)ロ 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ハ)ハ 許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
(2)特定建設業許可の場合
請負代金の額が 8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有している必要があります。
その要件は、以下の(イ)~(ハ)のすべてに該当する必要があります。
(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(ロ)流動比率が75%以上であること
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
【特定建設業の財産的基礎】
| 事項 | 法人 | 個人 |
| 欠損比率 | {│繰越利益剰余金│-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金は除く))}/資本金×100≦20% | {事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)}/期首資本金×100≦20% |
| 流動比率 | 流動資産合計/流動負債合計×100≧75% | 流動資産合計/流動負債合計×100≧75% |
| 資本金額 | 資本金≧2000万円 | 期首資本金≧2000万円 |
| 自己資本 | 純資産合計≧4000万円 | (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4000万円 |
※欠損比率の要件について、繰越利益剰余金が正である場合や、「資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益余剰金は除く)」の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合、要件を満たします(上記の計算式は不要です)。
※資本金額の要件については、申請日までの増資により基準を満たす場合は可となります。(事実を確認できる履歴事項全部証明書を添付する必要があります。)。
なお、特定建設業の許可更新にあたり、直前の決算期における財務諸表の内容が基準をすべて満たしていない場合、許可の更新できないので注意が必要です。
(3)各種語句について
自己資本…法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
資金の調達能力…担保とすべき不動産等を有していること等により、500 万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。
欠損の額…法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
流動比率…流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
資本金…法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社、合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。
【お電話はこちら】【お問い合わせメールはこちら】
6.欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得する際、先にご紹介した要件を満たしていても、許可を取得することができない場合があります。
以下のいずれか該当する場合、許可を取得することができません。
1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2. 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が次のいずれかに該当するとき。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したことにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3) 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(4)(3)の届出があった場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(8) 建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という)
(10) 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令(※)で定めるもの
(11) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(9)又は(11)のいずれかに該当するもの
(12) 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者のあるもの
(13) 個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者のあるもの
(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請の手続き代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。